マネージャーとしてチームを率いていると、日々、大小さまざまな「決断」の場面に直面します。
何をするか、どう進めるか、誰に任せるか。
でも、決められずに迷ってしまうマネージャーも少なくありません。
ただ、その「迷い」が積み重なると、チームに大きな混乱を生み出してしまうのです。
今回は「決断できないマネージャー」が抱えるリスクと、意思決定のために意識したい考え方、そして実践的なポイントをまとめます。
「決められない」が引き起こす現場の混乱
たとえばこんなこと、ありませんか?
- 新しい方針が出たけど、進め方が決まらず現場が動けない
- チームメンバーから相談を受けたけど、「もう少し考えさせて」と返し続けている
- 意見はたくさん出るけれど、誰も最終決定をしないからプロジェクトが止まる
こうした状況が続くと、チームには徐々にこんな空気が漂います。
- 「結局、誰が決めるの?」
- 「この案件、本当に進めていいの?」
- 「また止まった。どうせ今回も動かないでしょ」
やがて、メンバーのやる気が失われ、責任の所在も曖昧になり、チーム全体が鈍化していく…。
これは、決断を避け続けた結果、じわじわと起こる“チームの弱体化”です。
正解よりも「決めること」が大事な理由
マネージャーが意思決定をためらう背景には、「間違えたくない」「全員が納得してから決めたい」といった気持ちがあります。
でも、実は多くの仕事において、“完全な正解”は最初から存在しません。
大事なのは、「どれを選ぶか」よりも、
「いつ選ぶか」、「その選択肢をどう実行に移すか」。
決めないままでいると、機会を逃してしまうことも多いのです。
私が意識していた「意思決定のスタンス」
私自身、マネージャーとして動いていた頃は、
「スピード重視」の意思決定を意識していました。
もちろん、重大な判断は慎重になるべきですが、それでも私はこんな工夫をしていました:
◆ ゴールの日時を先に決めて「公言」する
「新しいサービス出したいな、いつまでに決める?」ではなく、
「8月に新サービスをリリースします。」と宣言してしまう。
できるかできないかではなく、やらざるを得ない状況にもっていきます。
そうすることで、意思決定に向けた逆算が始まり、チームも「この日までには準備が必要だな」と動けるようになります。
もしそれが間違っていてもいいんです。
間違っていれば取り下げればいいこと。その時になったら考えるという気楽さも大切です。
◆ 6割の完成度で動き出す
完璧を目指して立ち止まるより、
“まずやってみて、あとで改善する”方が、最終的には早く進む。
6割の完成度でリリースして、フィードバックをもとに仕上げていく方が、スピード感を持って前に進むことができました。
アンチを恐れて慎重になりすぎると何もできません。
それよりスピード感をもって物事を決断して進められることが大切です。
◆ 自分が最終判断者である覚悟を持つ
意見を聞くのは大事。
でも、最終的に決めるのはマネージャーの責任です。
「どうするか」はっきりしない状態が続くと、チームのストレスにもなります。
「もし失敗しても自分が責任を取る」と腹をくくって、決断していく姿勢が、結果的にメンバーからの信頼にもつながっていました。
決断の場数を踏んで「判断筋力」を鍛える
意思決定は、慣れれば慣れるほど、少しずつ“筋肉”のように鍛えられていきます。
最初は怖くても、場数を踏むことで判断の感覚が磨かれていきます。
迷いそうなときは、以下の質問を自分に投げかけてみるのもおすすめです:
- 「今、なにを決める必要があるのか?」
- 「一番優先すべきことはなにか?」
- 「この決断で、何を前に進めたいのか?」
あたまのなかで整理ができたらおのずと答えは決まっているはずなので
覚悟をもって意思決定を表明しましょう。
おわりに|「動けるチーム」は、決断から生まれる
チームがうまく回っていないとき、「誰も動かないな」「反応が悪いな」と思うことがあります。
でも、実は最初の一歩を止めているのはマネージャー自身だったりするんです。
「決めてくれる」「動かしてくれる」マネージャーがいるからこそ、メンバーも安心して前に進める。
そしてその決断力は、特別な才能ではなく、意識と行動で身につけられるスキルです。
だからこそ、怖がらずに一歩踏み出してみてください。
“決める”ことが、チームの動力になります。
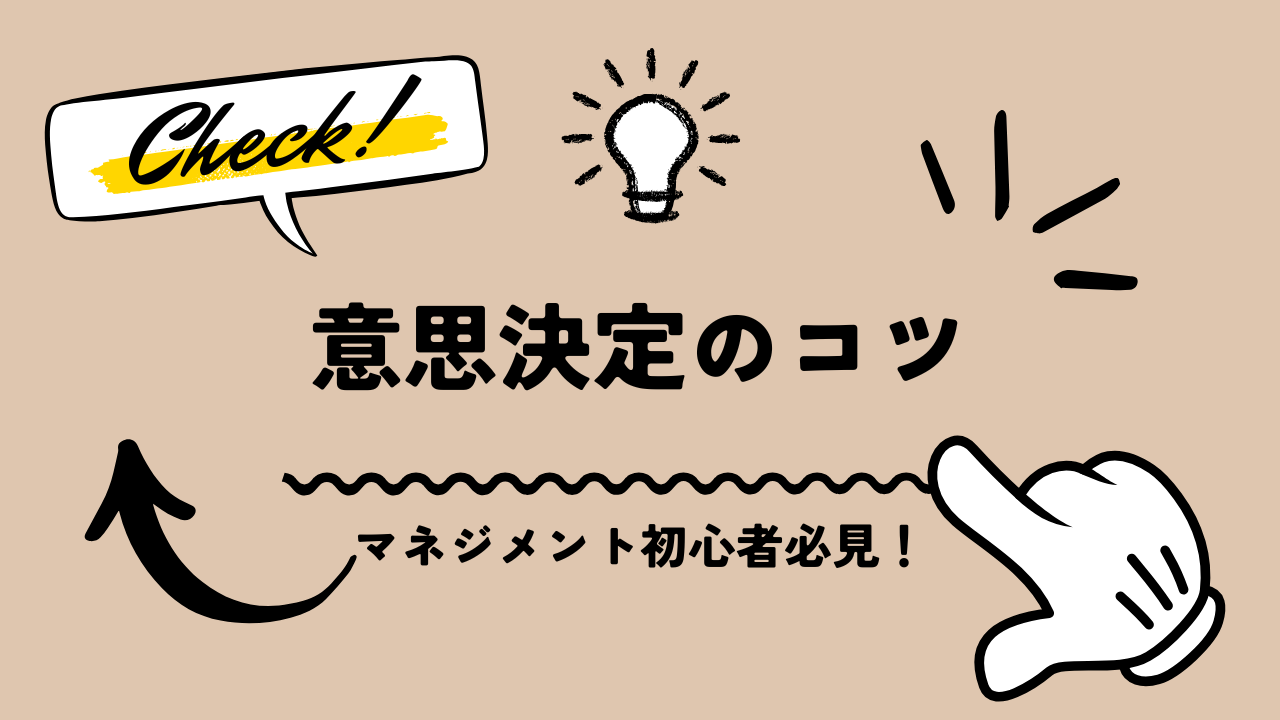
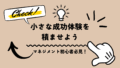
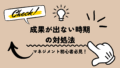
コメント