「目標設定ってどうしてた?」と聞かれることがあります。
でも、評価制度そのものは会社によって本当にバラバラなんですよね。
なので今回は、制度の話ではなく、
私がマネージャーとして“目標設定のときに意識していたこと”をまとめてみます。
ポイントは、
「チーム全体が前に進み、個人の評価にもつながる目標」をどう設計するかということです。
① 目標は“チームの施策を決めること”から始める
目標設定って、「個人がスキルアップするための目標」と思われがちですが、
実際は組織全体の目標を達成するための行動設計でもあると思っています。
だから私は、個人の目標を立てる前に、
チームとして“次の四半期に何をやるか”を全員で考える時間をつくっていました。
施策の内容は、上から降ってくるKPIや部門目標をベースに、
それをどう具体的な行動に落とし込むかを組み立てていきます。
多くの場合、マネージャーが指針を決めて割り振る形になると思いますが、
私はあえてチーム全員で施策を検討するようにしていました。
そうすることで、
メンバー全員が「このチームの目標は自分たちのものだ」と自然に思えるようになるんですよね。
たとえば、施策として出てくるのはこんなものです:
- 新サービスAの企画
- 既存サービスの改善
- セミナー登壇
- 社内スキルトランスファー
- ブログ更新やドキュメント整備 など
こうした施策を洗い出したうえで、
主担当・副担当をその場で決めるというスタイルにしていました。
よく「新人は補佐から」という考え方もありますが、
私は新人こそ主担当を経験してもらう方がいいと考えていました。
もちろん、いきなり丸投げではなく、
経験のあるメンバーや私自身が副担当として入り、
一人にさせない体制を整えるようにしていました。
このやり方だと、
新人は経験を積めるし、ベテランは育成の機会が増える。
チームとしても、役割が固定化しにくくなって、
全体のスキルアップにもつながるんですよね。
② 個人目標は“評価の基準”を意識して設計する
チーム施策と担当が決まったら、
次はそれを個人目標に落とし込むフェーズです。
ここで意識していたのは、
「評価のときに根拠として出せる目標になっているか?」という点でした。
● まずは、メンバーに“自分で目標案をつくってもらう”
目標って、マネージャーが与えるものじゃなくて、
本人が納得して取り組めることがいちばん大事です。
なので私はいつも、
「まずは自分で目標を設定してきて」と伝えていました。
そのときにあらためて確認するのが、
会社の評価制度(グレード要件や昇格基準など)です。
- 今のグレードで求められる行動は何か
- 次のグレードでは、どんな成果が求められているのか
- その中で、自分はどのレベルを狙いたいのか
この視点で考えてもらうことで、
目標が評価ときちんとリンクするようになります。
● 行動目標も、できるだけ“定量化”する
評価では、「なんとなく頑張ってた」だと伝わりません。
だからこそ、行動目標は数字や状態で定義しておくのがおすすめです。
たとえば、新サービスAの施策ならこんなふうに:
| 評価レベル | 具体例 | エビデンス |
|---|---|---|
| ★★★(2段階上) | 新サービスAが1件以上受注された | 受注件数 |
| ★★☆(1段階上) | サービス設計+営業資料が完成し営業部に提供できた | 営業資料 営業部とのMTG記録 |
| ★☆☆(現行水準) | サービス設計が完了し、社内報告を行った | サービス概要資料 社内報告MTG記録 |
| △(あと一歩) | サービス企画が承認され、設計フェーズに移行した | サービス企画資料 |
| ✕(未達) | 企画が形にならず、提案止まりで終わった |
“できた/できなかった”ではなく、
「どのレベルで成果が出たか」を明確にすることが評価時の説得力につながります。
さらに、評価時に使えるエビデンス(証拠)もあらかじめ決めておくと、
後から「説明しやすくなる」のでおすすめです。
● マネージャーの役割は“チャレンジの適切さ”を見極めること
メンバーが考えた目標を見たあとは、
マネージャーが「それが本当に適切なチャレンジか?」を見ていきます。
- 高すぎて挫折しそうではないか
- 低すぎて成長につながらない目標になっていないか
- 本人の性格や業務量に無理がないか
そのうえで、最終的に
「これならやりきれそう」と本人が納得できるレベルにすり合わせるのが大事です。
③ 目標は“チームで開示・共有”して、支え合う空気をつくる
目標がそれぞれ固まったら、
「じゃあそれぞれ頑張ってね」で終わらせないのがポイントです。
私のチームでは、
メンバー全員の目標を開示・共有する時間を必ずとっていました。
● 目的は“協力し合える土台”をつくるため
全員の目標を共有することで:
- チーム全体で「この目標を達成していこう」という意識が生まれる
- 「◯◯さん、この目標まだ手をつけられてないかも?」と気づける
- 「手伝おうか?」と自然に声をかけられる空気ができる
つまり、助け合いや声かけが自然に起こるチーム環境をつくるための土台になります。
● 全員で“全員の評価を上げにいく”空気をつくる
評価って、個人戦じゃなくて団体戦です。
チーム全体で個々人の目標を達成する仕組みをつくることができれば、
最終的にはチームの成果につながります。
そのために私は、
誰かの目標をサポートできたとき、それもきちんと評価に反映させることをメンバーに約束していました。
メンバーの困りごとに気づいて、助ける。
その動きもちゃんと私が拾って評価するからね。
こんなスタンスをチーム全体に浸透させていくことで、
「みんなで成果を出す」文化が少しずつ育っていきます。
● マネージャーの役割は“不公平感を生まない配慮”
目標を開示するときに大事なのが、
「納得感のある目標配分」になっているかどうかです。
- スキルや経験に偏りすぎていないか
- 明らかに負荷が重すぎる/軽すぎるメンバーがいないか
- 「なんで自分だけ…」という不満が出そうな状況じゃないか
こうしたバランスを取るのは、マネージャーの大事な役割。
しっかり調整したうえで目標を共有すれば、
やっかみやモヤモヤのない状態で、お互いを応援し合える空気ができていきます。
④ 達成だけが目的じゃない。チームの行動を“育てる目標”に
目標って「達成したかどうか」で評価されるもの、というイメージがあると思います。
もちろんそれも大事なんですが、私はもうひとつの視点――
「チームとして成長できる目標になっているか」もすごく大切にしていました。
● 新しい挑戦を組み込む
目標って、「今できることをしっかりやる」だけでは、
どうしても現状維持にとどまりやすいです。
だからこそ私は、目標の中に
“少しだけ背伸びする挑戦”を取り入れるようにしていました。
たとえば:
- 今までやったことのない業務にチャレンジする
- 他部署と連携して動く機会をつくる
- 発表や登壇などの“外に見える仕事”を組み込む
こうした目標は、結果が出なくても、やってみたこと自体に価値があると思っています。
目標って、「成果を出すため」でもあるけれど、
「成長のきっかけをつくるため」でもあるんですよね。
● メンバーの“方向性”にあった機会をつくる
あとはそのメンバーが今後どうなっていきたいかという方向性も考慮します。
- プレイヤーとして力を伸ばしたい人
- マネジメントに興味がある人
- 社内で顔を売っておきたい人
それぞれの希望や適性を踏まえて、
「チャンスになる目標」を一緒に設計していました。
やらされ感のある目標ではなく、
「やる意味がある」と思える目標にすることが、目標達成にもつながると思っています。
まとめ|目標設定で意識していたこと
目標設定って、ただ「これをやります」と決めるだけじゃなくて、
チームとしての目的と、個人の成長、評価制度のバランスを取る設計が大事だと思っています。
マネージャーとして私が意識していたのはこんなことでした:
- チーム全体の施策を全員で決める
- 成長と育成が両立する配置を意識して各施策の担当を決める
- 個人目標は、評価制度に沿って“証明できる形”で設計
- 目標は開示・共有し、チーム全体でサポートできる仕組みに
- マネージャーは、配分の公平さや、すり合わせの伴走役を担う
おわりに|評価につながる目標設定は“チーム設計”から始まる
評価される目標を立てるには、
メンバー本人が納得していること、チームの施策とつながっていること、
そして評価制度とズレがないことが大切です。
マネージャーとしては、
「目標を一緒に設計し、進みやすくする」ことが、すごく大きな役割だと思っています。
参考になればうれしいです。
関連記事
👉 昇給はチームメンバーが先。マネージャーとして私が大切にしていた評価との向き合い方
👉 チームは“雑談”から始まる。信頼関係をつくるためにしていた5つのこと
📌 筆者について
→ みそまねの自己紹介はこちら

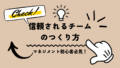

コメント