マネジメントをしていると、どうしても避けて通れないのが「成果が出ない時期」。
目標はある。努力もしている。やるべきこともやっている。
それなのに、成果が出ない。
そんな時期って、どんなチームでも必ずやってきます。
この時、マネージャーとしてどう関わるかは、チームのその後を大きく左右します。
焦って無理な指示を出すのか、黙って見守るのか。
今回は、「成果が出ない時期」のマネジメントについて、私自身の経験や考え方をもとにまとめてみました。
「成果が出ない」のは、どんな時か?まずは冷静に見極める
そもそも「成果が出ない」とは、たとえばこんな状態を指します:
- 数字目標が未達の状態が続いている
- 売上が伸び悩んでいる
- ユーザーの反応が鈍く、成果につながらない
状況によってその理由は様々です。
- サービスを立ち上げたばかりで市場に浸透していない
- 市場が飽和していて、既存の施策が通用しなくなってきた
- サービスにポテンシャルはあるけれど、営業や販促力が追いついていない
こうした要因を見極めるには、マネージャーとして冷静な目を持つことが欠かせません。
とにかく焦らず、まずは「今は成果が出にくい時期かどうか」を判断する必要があります。
事業計画に「成果が出にくい時期」を織り込んでおく
あらかじめ月単位・四半期単位で、目標や試算を立てておくと安心です。
数値の予測や行動計画を立てておけば、成果が出にくい時期も想定内にできます。
「この時期は立ち上げフェーズだから、数字が出ないのは当たり前」
「ここは準備期間。次の波に向けて積み上げている最中」
そう思えると、焦りが減り、必要以上に自分やチームを責めずに済みます。
また、業務を振り返る機会をきちんと持つことも大切です。
四半期末や月末など、一定のタイミングで予実を確認し、必要に応じて軌道修正する。
「どこがズレていたか」「改善すべきはどこか」を整理し、次のアクションに反映します。
原因分析は「責任追及」ではなく「改善のため」に
成果が出ないと、つい誰かのせいにしたくなることもあります。
でも大事なのは「何が悪かったか」ではなく「どうすればよくなるか」です。
振り返りの場は、できればチーム全体で行うのが理想です。
- サービスの内容に課題があるのか?
- プロモーションや営業の設計にズレがあるのか?
- 個人スキルやリソースの配分が足りていないのか?
こうした問いを、メンバーと一緒に考えることで、視点が増え、改善案が生まれやすくなります。
マネージャー一人で抱えず、オープンに議論できる空気をつくることも、立て直しの第一歩です。
上層部とのやりとりは、感情ではなく数字と改善策で
マネージャーが責任を持つべきなのは、成果に対する「報告の質」でもあります。
上層部へ報告する際は、
- 試算していた目標
- 実際の結果(予実)
- 分析と改善のための対応策
を冷静に整理し、感情ではなく「データと戦略」で語りましょう。
間違っても「部下が頑張ってくれなかった」などと言わないこと。
(もし特定のメンバーに明確な課題がある場合は、別途冷静に対応を)
あくまでマネージャーは「チーム全体」を背負い、必要な戦いは自分が引き受ける。
その姿勢が、結果的にメンバーを守り、信頼を得ることにもつながります。
チームを信じる。成果が出るまで何度でも試す
最後に大事なのは、「成果が出ていない=失敗」ではないということ。
今は出ていないだけ。
でも、やるべきことを着実にやっていれば、いつか成果は出る。
そのスタンスでいられるかどうかが、マネージャーの器量だと思っています。
「今は試行錯誤の途中だから大丈夫」
「次はきっとうまくいくはずだから、もう一回やってみよう」
そう言いながら、何度もトライアンドエラーを繰り返す。
その中でチームのスキルも整い、信頼関係も深まり、やがて成果がついてきます。
焦らず、でも止まらず。信じて、やり続ける。
成果が出ない時期こそ、マネージャーの本当の腕が問われるタイミングかもしれません。
だからこそ、静かに、でも強く、チームを支えるスタンスを持っていたいですね。
おわりに|「成果が出ない時期」にこそ、マネージャーの真価が問われる
数字が出ていないときこそ、マネージャーは「信じる力」を問われます。
成果がない=ダメ ではない。
成果が見えにくい=今は育っている途中 です。
マネージャーが焦らず、根拠ある見守りとフィードバックを続けられるかどうかが、チームの雰囲気と未来を大きく左右します。
ぜひ、そんなときほど「信じるマネジメント」を実践していってください。
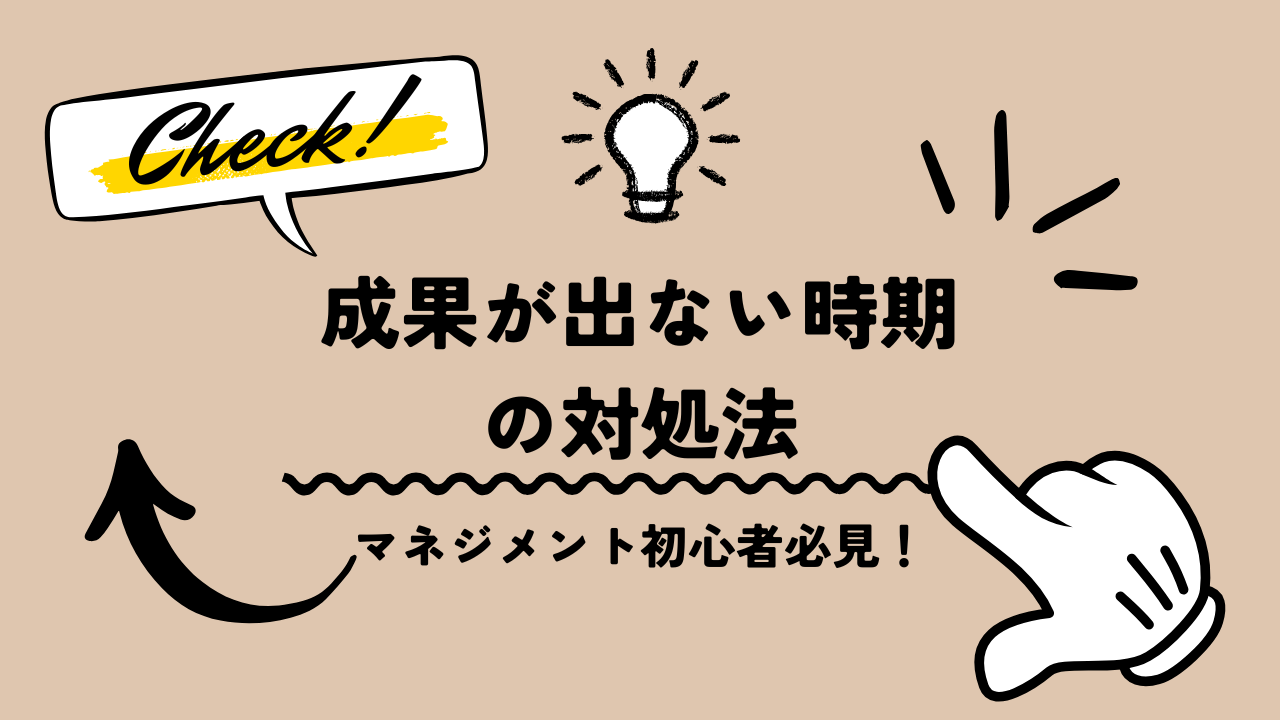
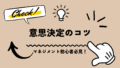
コメント