評価は“最後に自分がついてくる”ものでいい
若くしてマネージャーになる方って、
たいてい、今まで仕事に前向きに取り組んできて
その姿勢や成果が評価されてきた人だと思うんです。
だからこそ、マネージャーになって
「今度は自分が“評価する側”になる」という立場の変化に、
少し戸惑う人もいるかもしれません。
もちろん、自分も上司から評価され続ける立場ではあるのですが、
“自分がどう見られるか”ばかりに意識が向いてしまうと、チームが崩壊します。
- メンバーを評価した結果、自分が目立たなかったらどうしよう
- 先に昇格されたら困るかも
- 偉い立場をキープしてないと怖い
そんなふうに思ってしまう気持ちも、わかります。
人間なので初めにそう思うのは全然変なことじゃないし、普通です。
醜いことでもありませんよ。
でも、その考えはいったん脇に置いて大丈夫。
自分の評価を気にして動かなくても、
チーム全体を正しく支えていれば、自然と自分への評価もついてきます。
表立った活躍をしていなくても、
「このチーム、なんかすごいぞ」
「誰がまとめてるんだ?」
と、自然と気づいてもらえます。
マネージャーの役割は自分の活躍ではなく、
チームを活躍させることです。
それが会社や上層に認知されたとき、
結果として、自分の評価もちゃんとついてきます。
まずは昇給制度を理解する
昇給や評価って、つい「頑張ってるかどうか」で決まるように思われがちですが、
基本的には“制度”に沿って判断されるものです。
だからこそ、マネージャーとして
社内の昇給ルールをしっかり把握しておくことが大前提になります。
たとえばこんな項目:
- 昇給テーブルやグレードなど、社内の評価定義
- 各グレードで求められる仕事内容や水準
- 昇給の条件や判断基準(成果、期間、行動など)
これらは言わば、ゲームのクリア条件みたいなもの。
ルールを知らずに「がんばってるのになんで昇給できないの?」と思っても、
うまくいかないのは当然なんですよね。
昇給は「次のグレードの仕事をしてるかどうか」で判断される
多くの会社での昇給交渉って、こういうロジックです:
「今の仕事を十分にやれている」
ではなく、
「もう一つ上のグレードの仕事をすでにやっている」
→ だから昇給させてね
つまり、“先に動いて、あとから対価をもらう”スタイルが基本。
これを知らずに「がんばったんだから上げてよ」と訴えても、
「今の等級でできることをやってくれてるだけだよね」と見なされてしまうこともあります。
古い文化の会社だったとしても
もちろん、会社によっては
「上司に気に入られていれば昇給する」
みたいな空気感が残っているところも、ないとは言えません。
でも、そういうのってフェアじゃないし、誰も納得できない。
だから私は、
「制度に沿って、理屈で説明できる評価」を大切にしていました。
たとえば:
- 上のグレードで求められる仕事をすでに担っている
- 数字や成果で、それが証明できている
ここまでできていれば、
「もう昇給させるしかないよね」と理屈で認めざるを得ない状態をつくれます。
制度を理解して、行動で証明する。
それが、メンバーを昇給させるための基本です。
マネージャーとしてその流れを理解しておくことで、
「チームを守る力」もぐんと強くなると思っています。
メンバーにも制度を共有する
マネージャー自身が制度を理解することは大前提ですが、
その知識は、必ずメンバーにも共有しましょう。
というのも、
「頑張ってるのに評価されない…」と悩む人の多くは、
そもそも評価のルールを知らないまま働いているから。
目の前の仕事に一生懸命になりすぎて、
「何をどうすれば昇給できるのか」が見えていない人って結構多いんです。
昇給の“仕組み”を先に伝えておく
私は、評価直前ではなく、期の始まりやクオーターのスタート、目標設定のタイミングなど、
できるだけ早い段階で評価の仕組みを伝えるようにしていました。
「この会社では、“今の仕事をちゃんとやる”だけでは昇給できないよ」
「もうひとつ上のグレードの仕事を“すでにやってる”って証明できることが、昇給の基本なんだよね」
この話を先に共有しておくことで、評価期間中の行動の解像度が全然違ってきます。
評価は「見え方」も大事な戦略
評価って、「がんばり」や「真面目さ」だけでは測れないんですよね。
だからこそ、制度のロジックとあわせて
“どうやってその仕事を証明していくか”を一緒に考えることが、マネージャーの役割だと思っています。
- どんな仕事が「ひとつ上のグレード」なのか
- それをどう実績として残すか
- 誰にどう見せておくか
このあたりを、目標設定の段階でしっかり話し合っておくと、
評価の時期になって慌てることもありません。
メンバーが昇給できるかどうかは、
“がんばったか”じゃなくて“戦略的に証明できたか”。
そのスタート地点を、マネージャーが一緒に整えてあげることが大切なんだと思います。
評価期間中にやっていたこと(見せ方とブランディング)
評価の仕組みを理解してもらったあとは、
実際の業務の中で“見える形”で成果を積んでもらうことが大切になります。
いくら良い仕事をしていても、
それが社内で認知されていなければ評価にはつながりにくい。
だから私は、評価期間中に“見える化”を意識した動き方をしていました。
各業務の主担当をメンバーに任せる
私のチームでは、新サービスの企画・営業資料づくり・プリセールス・納品など
多岐にわたる業務を行っていました。
その中で私は、メンバー個々の適性を見ながら、それぞれに主担当の役割を任せていました。
- リリース報告や社内プレゼンも、マネージャーではなく“その担当メンバー”が行う
- セミナーや社内勉強会なども、登壇のチャンスがあればメンバーを前に出す
主役はあくまでメンバー。
私は裏で調整やサポートにまわるように意識していました。
未経験な業務でも“挑戦できる環境”を整える
もちろん、初めて経験する業務を任せることもあります。
その際には、必ず副担当をつけるようにしていました。
- 副担当には、私または経験豊富なメンバーを配置
- 「一人で抱えさせない」体制を意識
- 副担当にも「やったことは評価に書いていいよ」と伝え、全員が成果を得られる構成に
この運用を続けることで、
主担当だけでなく、チーム全体で“評価されるポイント”を増やしていくことができます。
他部署との接点もメンバー主導でつくる
評価は“社内での印象”にも左右されるので、
他部署とのつながりを持つことも意識していました。
- プロジェクトの連携や調整役も、できるだけメンバーに任せる
- 会議やチャットのやり取りの回数を増やすよう促す
- 「あの人よく見るな」と、他部門に印象づける
こうした横のつながりが広がると、
自然と「評判」や「信頼」がにじみ出るチームになっていきます。
上層部への“間接アピール”を仕込む
また、私は上層部への報告の場で、
意識的にメンバーの名前を出すようにしていました。
「今回の〇〇、担当の△△さんがすごく良い動きをしてくれて」
「□□の改善案は××さんからの提案なんです」
こうした“自然な会話の中でのアピール”を仕込むことで、
メンバーの努力が経営層の目にも入るようになっていきます。
マネージャーの仕事は、自分が前に出ることではなく、
メンバーが活躍できる場を整え、正当に評価される仕組みをつくること。
その意識で日々の動きを組み立てていくと、
チーム全体の評価は確実に底上げされていきます。
評価の準備と提出前のチェックポイント
評価のときに大事なのは、「がんばりました!」の一言ではなく、
“証拠と数字”で語れる状態にしておくことです。
たとえば:
- 売上/商談/KPI達成率などの実績
- 定性的な成果のエピソード(改善・提案・工夫)
- 他部署や上層部からのフィードバック
これらをあらかじめ集めておけるよう、
目標設定の時点で「何を成果として証明するのか」もすり合わせていました。
評価作文の添削も“勝負前の仕上げ”として必須
提出前には、メンバーが書いた評価作文を必ずチェックしていました:
- 全社共通の“評価軸”で伝わっているか
- 事実とのズレがないか
- 書き漏らしがないか
- 「ひとつ上の仕事をしていた」という証拠が含まれているか
評価資料は、メンバーの実力を伝える勝負の場。
ここを丁寧に仕上げることで、メンバーの頑張りが正しく伝わります。
評価権がないマネージャーだったときは?
実は、私も一部の期間は「評価権限がないマネージャー」でした。
でも、やっていたことは基本的に変わりません。
- 目標のすり合わせ
- 日々の証拠集めと社内への“見せ方”支援
- 評価作文の添削
- そして…評価者に向けた「評価依頼書」の提出
“評価依頼書”は私のオリジナルツールでした
会社に正式なフォーマットがなくても、
「このメンバーは昇給に値する」と、
自分の言葉で理由を書いて、社内の評価者に届けていました。
現場で一番メンバーを見ているのは自分だから。
伝えなければ、正しく評価されない。
だから私は、独自に評価依頼書を作成して提出していました。
上司もそれを補助資料として活用してくれて、
しっかりとメンバーが評価される流れにつながっていたと思います。
まとめ|評価されるチームをつくるために、私が意識していたこと
📝 マネージャーとして、こんな動きをしていました:
- 社内の昇給制度を把握し、メンバーにも共有する
- 目標設定時に「何を成果として証明するか」を一緒に考える
- 日々の業務ではメンバーを主役にし、活躍の舞台を譲る
- 他部署との連携や社内プレゼンなど、社内で“見える活動”を支援する
- 評価作文の添削で、実績と成長がしっかり伝わるよう整える
- 評価権がなくても、補助資料(評価依頼書)で後押しする
メンバーが正しく評価されるようにサポートすること。
それが、マネージャーとしての私の仕事でした。
おわりに|チームメンバーが先、マネージャーは後
マネージャーって、昇給に対して直接的な“結果”を出せる立場じゃない。
でも、“影響”はものすごく大きい。
メンバーが評価されやすくなるように、
仕組みをつくって、仕掛けて、整えて、届けていく。
それができるのは、現場に一番近いマネージャーだけです。
だから私は、
メンバーが正しく評価されるために、自分ができるすべてのことをやる。
そんなスタンスで、日々マネジメントに向き合っていました。
参考になれば幸いです。
📌 筆者について
→ みそまねの自己紹介はこちら
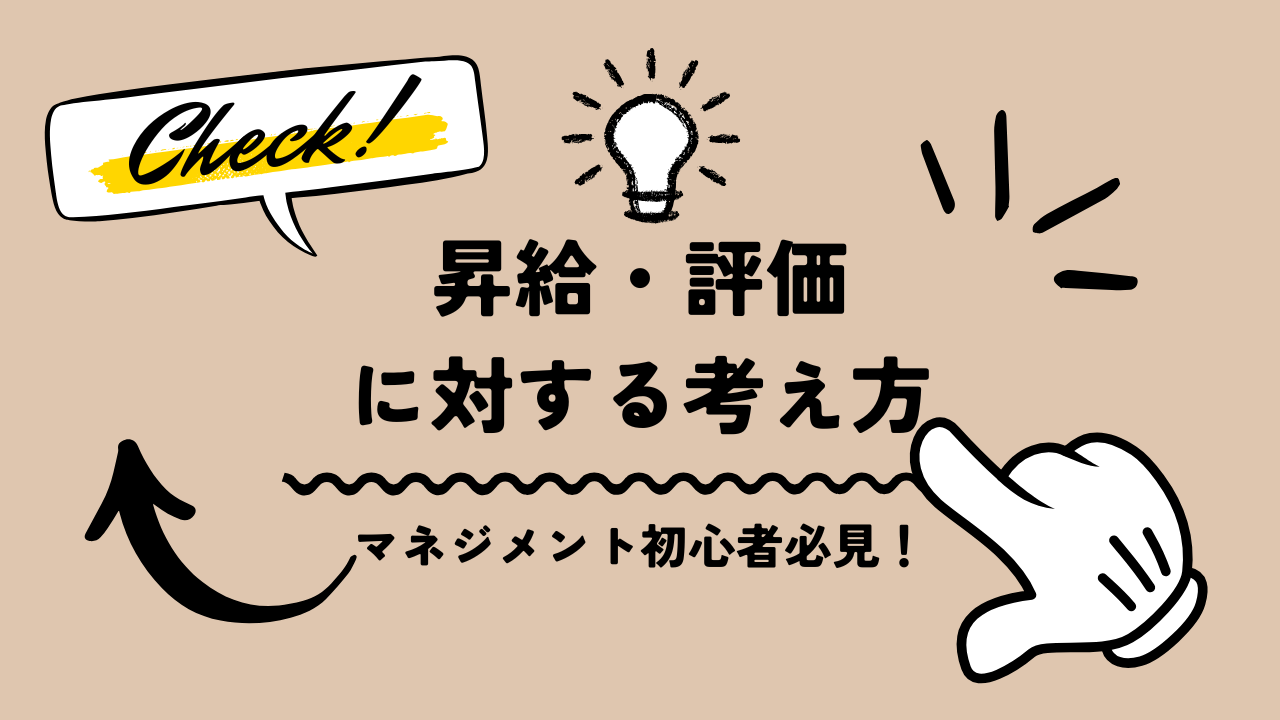
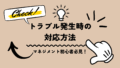
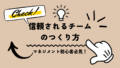
コメント