トラブル対応の現場では、「これだけはやらないようにしよう」と思っていたことがいくつかあります。ここでは、私や周囲の経験から「これは避けたい」と思う行動、そしてどう切り替えると良かったかをまとめてみました。
1. 犯人探しに走る
トラブルが起きると、つい「誰がやったの?」と犯人探しをしたくなるもの。
でもこの“犯人探し”は、チームの空気を悪くし、問題解決を遅らせます。
メンバーも「怒られる」「隠そう」となり、正しい情報が出てこなくなります。
何が起こったのかを確認した際に、ミスの原因が人的なものだと分かったときにも、
その場では絶対に怒ったり責めないようにしていました。
「ミスは誰でもあるし、まずはリカバリーが最優先。あとで一緒に振り返ろう」と伝えて、
とにかく安心させ、トラブルに対応することを心がけました。
ここがポイント!
大事なのは「今は原因追及より、現場の立て直し」。
ミスの当事者にも「まずは復旧に集中してもらおう」と、空気を落ち着かせる役割を意識していました。
2. パニックになって現場を混乱させる
マネージャーが焦ってしまうと、現場全体が不安になり、指揮系統も乱れます。
実はこれが一番トラブルの収束を遅らせてしまう要因だったりします。
トラブルの度合いによっては、内心めちゃくちゃ焦ることもあるかもしれません。
私も何度かそういう場面に出くわしました。
そんな時は「どしっと構えた“かっこいい自分”を演じる」気持ちで、表面上は落ち着きを見せるようにしていました。
マネージャーが落ち着いていると、チームのみんなも冷静になって次の行動に移りやすくなります。
ここがポイント!
どんなに不安でも、「落ち着いて見せる」のが現場の安定に一番効きます。
演技でもOK!困った時こそ、一呼吸おいてどしっと構えてみてください。
3. メンバーを人前で叱責する
人前でメンバーを叱責したり、悪口を言ったりするのは絶対に避けましょう。
当たり前ですがメンバーに恥をかかせることになり、
自己肯定感が損なわれるだけでなく、今後の業務のパフォーマンスにも影響します。
またマネージャーにもデメリットがあります。
「人前で怒るな」っていうよくあるマネジメントノウハウは
若手の人はマネージャーじゃなくても、一般論として意外と知ってます。
やった瞬間に現場の信頼感が一気に崩れますし、メンバーからの信頼も地に落ちます。
私もかつて上司にメンバーの前でやられたことがありました。
実際、他のメンバーもその場でドン引きし、その上司の信頼が失われてしまう結果になっていました。
自他ともに良い結果を生まないので、つい感情的になることがないよう自制しましょう。
ここがポイント!
注意やフィードバックが必要なときは、必ず改めて1対1の場で落ち着いて話す。
それだけで、信頼関係は保たれますし、本人も冷静に受け止めてくれやすくなります。
4. 十分な情報を集めずに謝罪・言い訳をする
トラブルが発生したとき、すぐに謝ったり、反射的に言い訳をしてしまうのも危険です。
状況をよく把握せずに謝罪してしまうと、そのまま“全部のうち責任”として話が進んでしまうことも。
私自身、「お客様は大切だけど簡単には謝らない」ということを大事にしていました。
謝罪は本当にこちらに非があると確定したときにだけ行い、
それまでは冷静に事実を確認し、どこにどんな責任があるかを整理してから対応していました。
言葉では謝らないけれど、真摯な対応をすることは大切なので、
横暴にならないようには注意してくださいね。
「恐れ入りますが…」など、「ちょっと申し訳ないけど謝っているわけではない」印象の言葉を代わりに使うのはおすすめです。
ここがポイント!
“まず情報整理、謝るのは非が確定してから”。
これを徹底するだけで、余計なトラブルや誤解をかなり防げると思います。
5. 一人で抱え込む・自分だけで解決しようとする
「全部自分で解決しよう」と頑張りすぎるのもNG。
トラブルの規模によっては、一人の力ではどうしようもないこともあります。
人を巻き込んででも何をしてでも、迅速にリカバリーがをすることが最優先。
それがお客様ファーストの行動でもあります。
私も「人を頼るのがマネージャーの仕事」と割り切っていました。
他部署や上司、必要な関係者には早めにヘルプを出し、
みんなで一刻も早くリカバリーできるように動いていました。
ここがポイント!
“助けを呼ぶのは恥じゃない”。
適切なタイミングで巻き込むことで、より早く問題解決に近づけます。
6. 上層部や関係部署への報告を後回しにする
トラブルが発生すると、「まだ自分たちでなんとかなる」と思って報告を後回しにしてしまいがち。
でも、これがあとで「なんで早く言わなかったの?」という話につながります。
私自身、トラブルの影響範囲が広がりそうな時は、なるべく早めに上層部や関係部署に状況を共有していました。
事前に報告しておくことで、必要なサポートや指示ももらいやすくなるし、最悪のケースにも備えやすくなります。
ここがポイント!
「早め早めの共有」が、会社もチームも守るコツです。
7. トラブル後のケアを怠る
トラブルが収束したあと、「はい終わり」で放置するのも避けたいところ。
ここでケアをしないと、トラブルがトラウマになりメンバーが次の挑戦に臆病になることもあります。また、自己肯定感も下がったまま物事へのモチベーションが下がってしまうことも。
私は必ずフォローの時間を作りました。
必ず声をかけて「大丈夫だった?」「助かったよ」と伝える時間を作る。みんなでちょっと雑談する、お疲れ様ランチに行くなど、「切り替えの場」を設けるのがおすすめです。
また業務の振り返りの場を作って、
「今回何が学びだったか」「今後どうすればいいか」を一緒に考える時間をとっていました。
一度立ち止まることで、成長のきっかけにできると思っています。
ここがポイント!
トラブルを悪い思い出だけにしないよう「振り返りの時間」でケアしましょう。
メンバー・マネージャー共に「今回の学び」や「次に活かせること」があるはずなので
一緒に振り返ることで、失敗を“成長の経験”に変えるきっかけにもなります。
おわりに
トラブル対応でやりがちなNGを避けるだけでも、現場の雰囲気や成果が大きく変わります。
「これやっちゃいけないな」と思うことは、意識して避けるだけでも十分。
ぜひ、みなさんの現場にも取り入れてみてください!
関連記事
- トラブルが起きたとき、マネージャーだった私がやっていたこと
- マネージャーとして意識していた「柔と剛のバランス」って何?場面ごとの切り替え方を紹介!
- 1on1で信頼関係を築くコツ|マネージャーのリアルな現場ノウハウ
📌 筆者について
→ みそまねの自己紹介はこちら
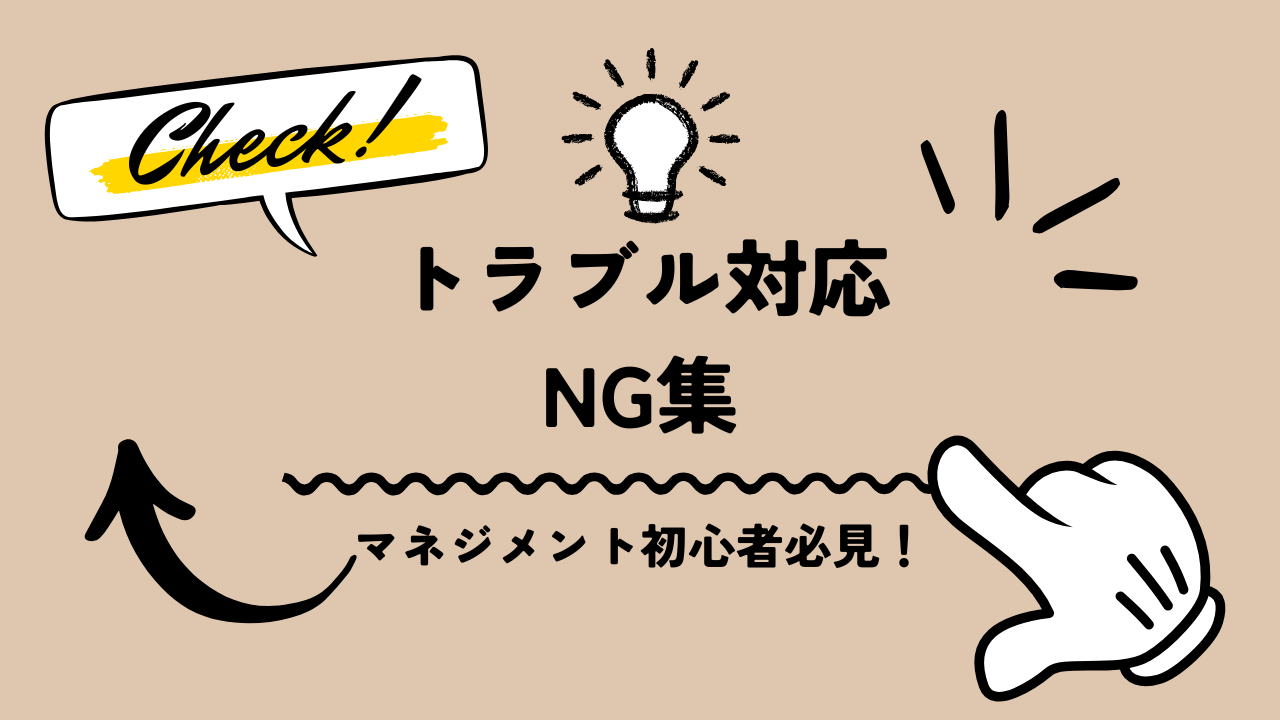

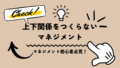
コメント